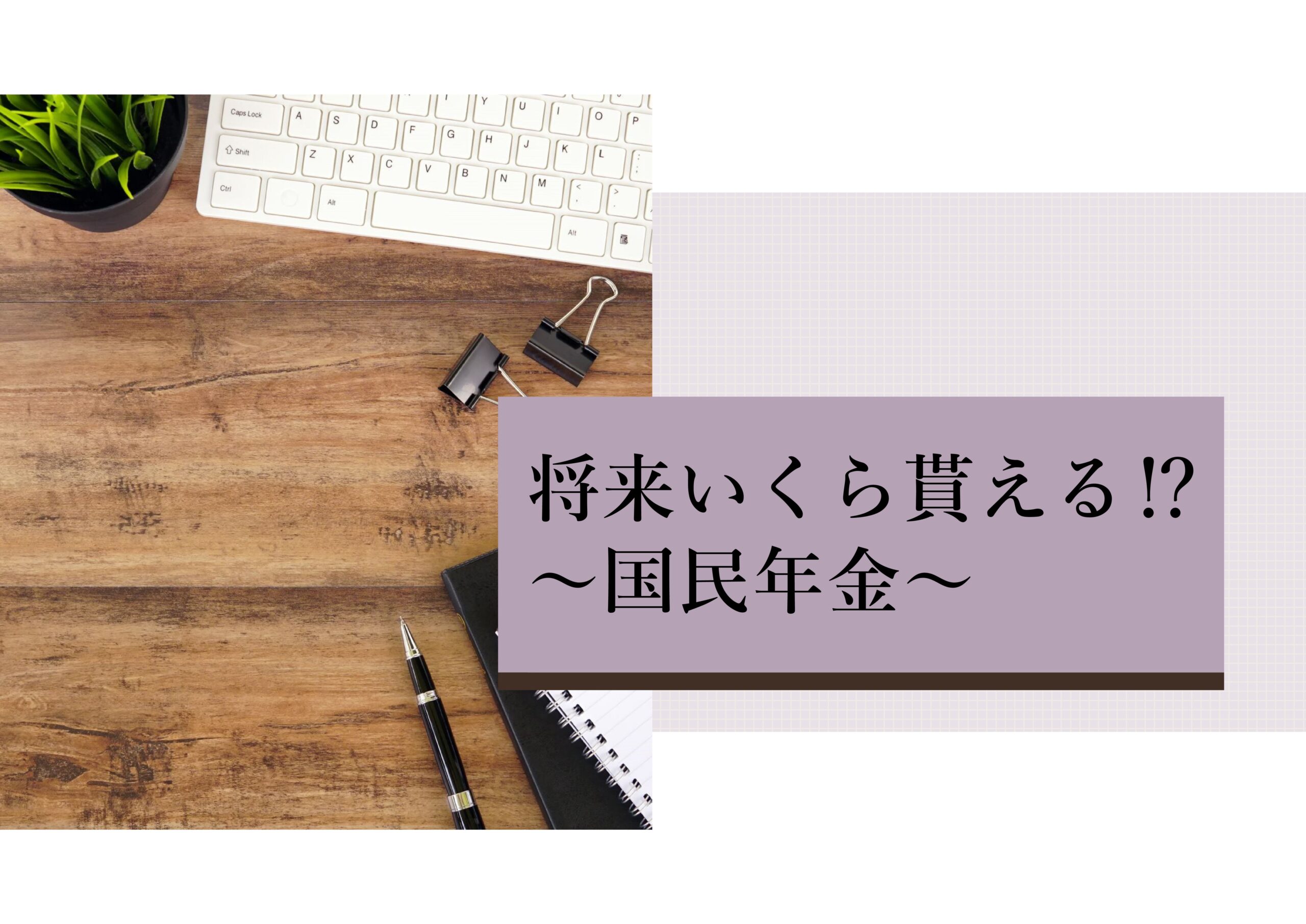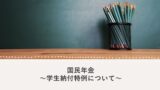皆さん一度は聞いたことあるワードだとは思います。
将来の給付額や、月々の納付額についてよくわからないことは多いと思います。
実際に私も社労士の勉強をするまでは内容について全くの無知でした。
そこで今回は、超簡単に内容をまとめたいと思います!!
国民年金とは

日本に住んでいる20歳~60歳のすべての方が加入する公的年金で、一般的に会社員が加入する厚生年金の基礎部分という認識を持たれる場合が多いです。
◆国民年金の被保険者には3種類あります。
・第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生、無職の方 等
・第2号被保険者・・・会社員・公務員などの厚生年金の被保険者
※第2号被保険者として厚生年金保険料を払っている期間は国民年金保険料を納めている期間としてカウントされます
・第3号被保険者・・・いわゆる社会保険の扶養に入っている20歳以上60歳未満の配偶者
ここで注目したいのが、学生や無職の方でも加入必須という点です。学生は納付猶予という制度があり、将来遡って納付することが可能になります。
手続き漏れ等で未納期間にならないように注意しましょう。この未納期間が障害年金受給の妨げになる場合がございます。
国民年金から給付される年金
国民年金は老後、基礎年金として納付実績に応じた金額が支給されます。
それ以外にも障害を負った際や、死亡時に遺族に支給される年金もございます。
老齢基礎年金
国民年金に加入していた方が原則65歳~受給できる年金です。
・支給要件
保険料納付済期間+保険料免除期間 が10年以上あることが条件
この保険料免除期間とは、生活保護を受けていたり障害等により国民年金の納付が免除されている期間を指し、学生納付特例期間も含まれます。
学生納付特例については下記をご参考にどうぞ☟☟☟
・支給金額(年額)
【780,900円 × (納付月数/480ヵ月)】が支給額となります。
毎年物価等の影響を考慮し、一定の率で価格改定がされますがおおよそは上記金額の通りとなります。
また、学生納付特例期間に関しては追納をしない限り、年金受給額には反映されませんのでご注意ください。
・受給の繰り上げ、繰り下げ
老齢基礎年金の受給は原則65歳からですが、受給額を一定の割合で減額することで65歳より早めて受給することが可能です。
また、65歳以降に受給することで一定の割合受給額を増やすことが可能となります。
◆繰り上げ受給
最大で60ヵ月繰り上げ可能(=60歳から受給開始可能)
⇒減額率・・・0.4%(1ヶ月あたり) ※昭和37年4月1日以前生まれの方は 0.5%(1ヶ月あたり)
☞具体的には
平成4年12月生まれ方が64歳になった月から受給する場合(⇒12ヵ月間繰り上げ)※未納期間、保険料免除期間が無いものとする
・・・780,900円(100%-0.4%×12ヵ月) × 改定率 ≒ 743,500円(年額) となります
◆繰り下げ受給
最大で120ヵ月繰り下げ可能(=75歳到達まで繰り下げ可能)※昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げ上限年齢が70歳となります
⇒増額率・・・0.7%(1ヶ月あたり)
☞具体的に
平成4年12月生まれ方が74歳になった月から受給する場合(⇒108月間繰り下げ)※未納期間、保険料免除期間が無いものとする
・・・780,900円(100%+0.7%×108ヵ月) × 改定率 ≒ 1,371,300円(年額) となります
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やケガで障害が残った場合に支給される年金です。
・初診日要件 ・保険料納付要件を満たし、1級または2級の障害認定を受けた場合に受給できます。
金額はこれまでの国民年金保険料の納付実績にかかわらず、
1級・・・780,900円×1.25×一定率
2級・・・780,900×一定率 となります。
また、18歳未満の子供の有無により、子の加算があり、第2子まで約225,000円追加で支給され、第3子以降一人当たり約75,000円追加で受給可能となります。
遺族基礎年金

国民年金加入中の方が亡くなった場合に遺族に支給される年金です。
死亡した被保険者が・死亡日要件 ・保険料納付要件を満たし、かつ、【18歳未満の子のある配偶者】もしくは【18歳未満の子】でないと受給できません。
支給金額(子の加算含む)に関しては、障害年金と同様となります。
また、配偶者が遺族年金を受給する場合、18歳未満の子があることが条件のため、必ず子の加算は受けられるということになります。
国民年金の保険料額
国民年金保険料に関しては、第2号、第3号被保険者に関しては免除されておりますので、支払う必要はございませんが
第1号被保険者に関してはご自身で納付する必要がございます。
保険料額は17,000円×改定率となっており、令和6年度は16,980円が1ヶ月の納付額になります。
納付方法は納付書、口座振替、クレジットカード等 ご自身で選ぶことが可能です。
まとめ
今回は基礎年金の種類や受給額、保険料額についてまとめてみました。
ざっくりとした受給額について理解していただけたら幸いです!!
年金関係は色々なルールが入り乱れているため非常にややこしいです。。。
手続きはご自身で行わないといけないため、抜け漏れが無いようにしましょう^^
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせからご連絡お待ちしております。
皆様のお金に関する不安が少しでも解消されることを願っております!!